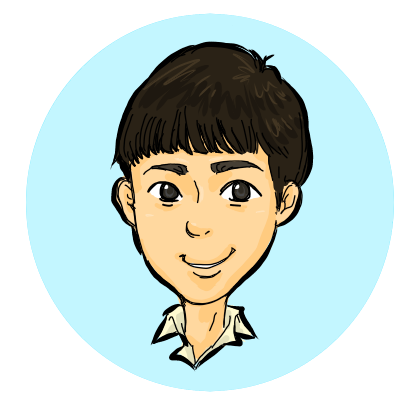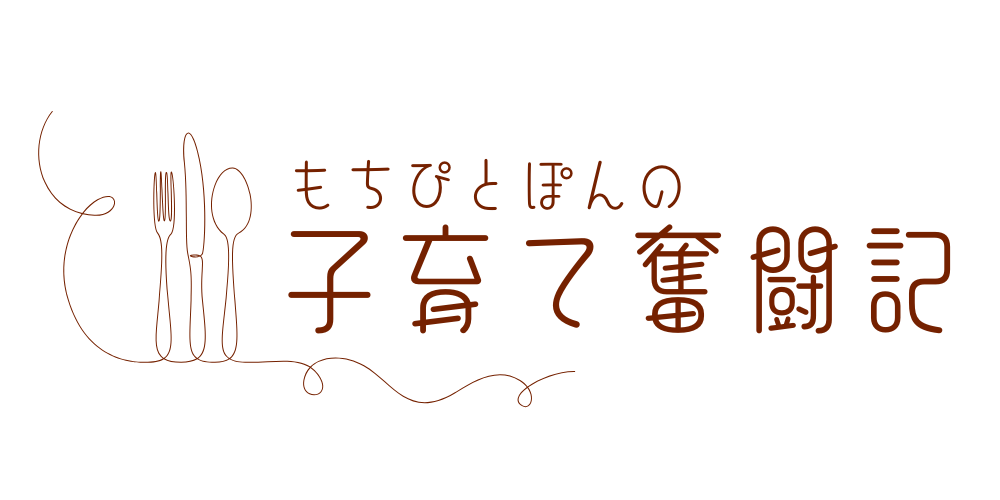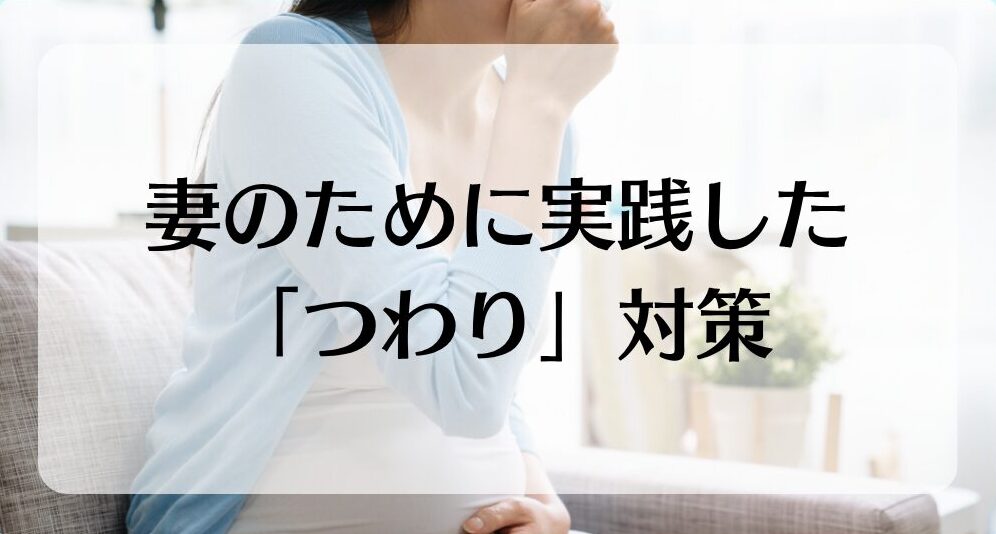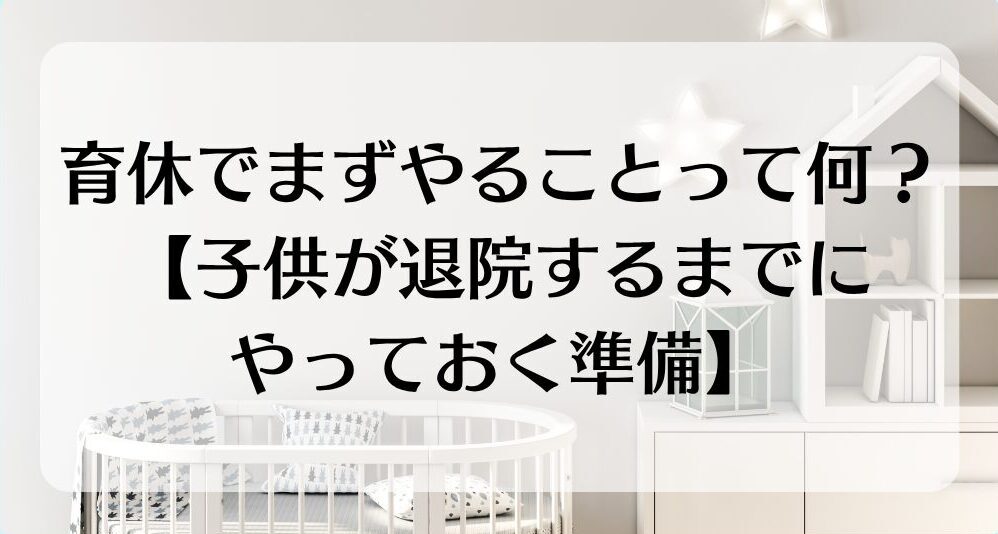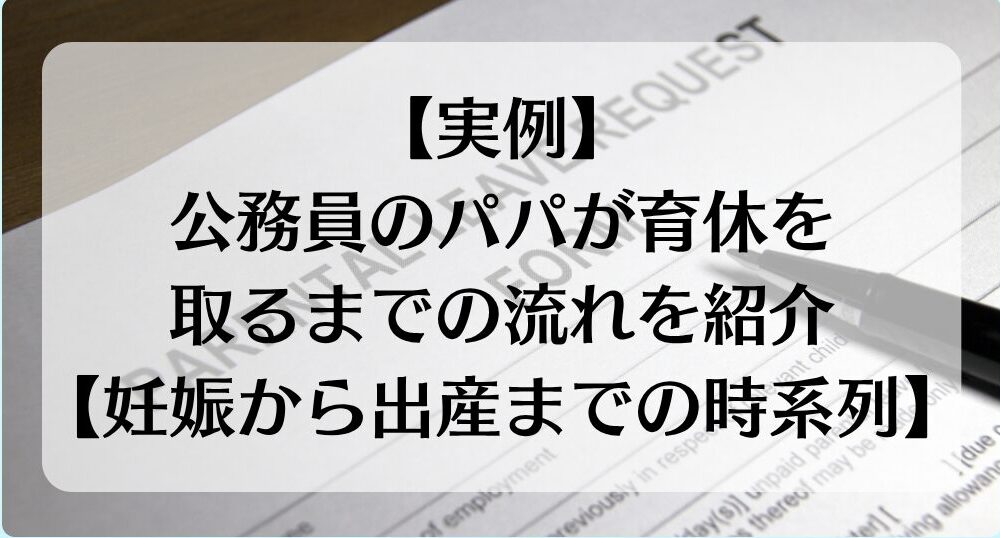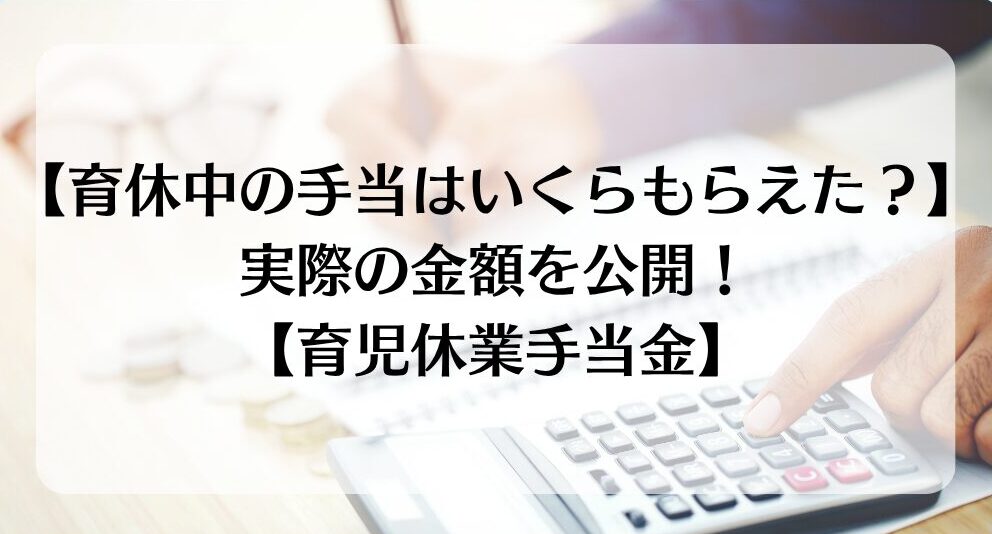男性が育休を取得するメリット5選【育休経験者が解説】

こんにちは、ぽんです。
今回は、男性が育休を取得するメリットを5つ紹介します。
育休は子供に深く関わったり奥さんをサポートしたりと色々なことができる反面、職場への迷惑などを考えるとどうしても育休取得をためらってしまう人も多いと思います。
だからと言って、取得しないことで後悔することもあると思うので、育休のメリットと天秤にかけつつ判断するのが良いと思います。
社会的には推進されている制度なので、これからは当たり前の制度になっていくこと、1人でも多くの方が育休を希望することを願っています。
育休のメリットは様々あると思いますが、私が育休を経験して感じた想いなども加味して5選を選びました。
育休取得を悩んでいる方の後押しになれば嬉しいです。
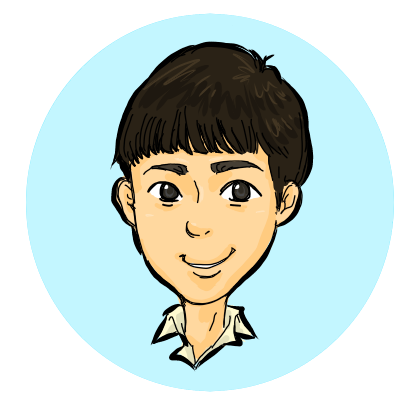
早速ですが、メリットを5つ発表します。
①子供の成長を日々感じることができる
②子供の成長に良い影響を与える
③妻との育児経験値の差を縮めることができる
④夫婦の絆が深まる
⑤「急」な何かに対応しやすくなる
それではひとつずつ解説をしていきます。
①子供の成長を日々感じることができる

産まれたばかりの子供は、日々大きく成長していきます。
身長や体重はもちろんですが、顔つきや手足の動かし方、反応の仕方や表情など、細かい部分でも日に日に変化していきます。
例えば平日の5日間が仕事だと、帰宅後の様子は寝てる場面がほとんどで、細かい変化どころの話ではないと思います。
土日を迎えると子供は5日分成長しているので、かなり大きな変化が起きている場合もあるでしょう。
育休であればそんな変化も見て感じることができる。
やっぱり、最大のメリットは「子供の成長を日々感じることができる」だと思います。
我が子の変化を実際に見て、日々成長を感じられることは嬉しいですし、幸せなことだと思います。
細かな様子を知ることは今後の育児にも大きく影響してくるので、育児に深く関わるには子供と接する時間をなるべく増やす必要があります。
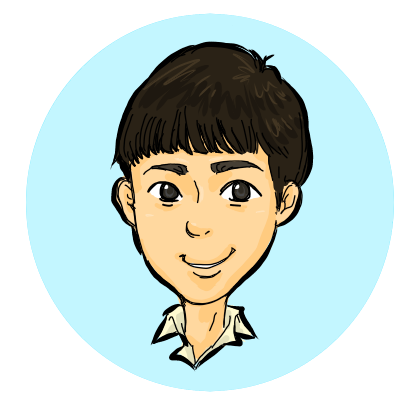
次に成長面だけでなく、私が気付けた子供の変化についても紹介します。
私が気付けた子供の変化
実際に自分が育児をすることで、変化を感じることができる瞬間がいくつもあると思います。
私の場合は、授乳・排便・肌トラブル関係で変化を感じてサポートできました。
授乳
我が家は長男と次男ともに完全ミルクでした。
それもあって、私が授乳を担当することも多くありました。
毎日、何回と授乳に関わっていると、子供のミルクを飲むペースや飲める限界、お腹が空いた時の様子などが分かるようになってきました。
妻と同じように授乳に関わることができたので、ミルク量を増やすタイミングや乳首のサイズ、1日の授乳スケジュールなどを妻と一緒に考えることができました。
排便
排便については、1日の回数や色・性状(固さなど)などの変化に気付くことができるようになりました。
便の変化は体調の変化にも深く関係するので、場合によっては病院受診などの指標にもなります。
便が出ず便秘気味だとミルクの飲み具合にも影響がでてくるので、綿棒浣腸をしてウンチを出してあげたりもしました。
綿棒浣腸もはじめは恐る恐るやっていましたが、長男・次男と経験値が増えたので手早くできるようになりました。
肌トラブル
毎日の沐浴や着替えをしていると、湿疹(しっしん)や汗疹(あせも)、傷などが新しくできていないか気付くことができます。
肌の様子によっては保湿剤をより丁寧に塗ってあげたり、薬を塗って対応することもあります。
薬は病院で処方してもらえるので、定期受診などで奥さんが先生に伝え忘れていたときは話を振ってあげることもできました。
同世代の赤ちゃんとの成長も比較することができる
育休を取得していると、子供に関する様々なイベントに参加することができます。
特に検診については、参加することでプラスになることがたくさんあります。
身体測定は子供の成長を数字で見ることができますし、保健師さんにも色々相談ができるので心配事の解決やヒントが見つかります。
月齢に合わせて、発達の話や離乳食の話なども聞くことができました。
同じ誕生月くらいの子供たちが集まるので、他の子供の成長具合も見れます。
また、状況によっては子供たちの両親とも知り合いになることが可能なので、ママ友やパパ友に発展することがあるかもしれません。
長男のときは育休が2ケ月弱だったので、検診の日は休みを入れて参加していました。
検診に来る親を見てみると母親だけの参加がほとんどで、夫婦で参加している人はいませんでした。
他の自治体の検診の様子が分からないので正確なことは言えませんが、場所によっては病院で検診を受けるところもあるようです。
その場合でも色々とプラスになることはあると思うので、参加できるならしてみてもいいのかと思いました。
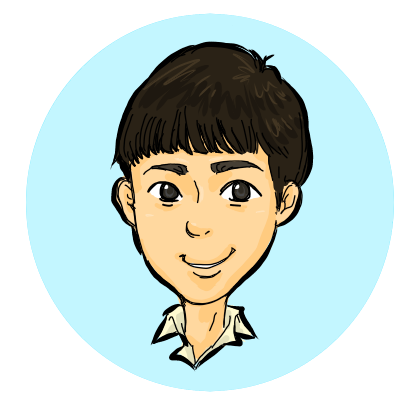
②子供の成長に良い影響を与える

パパが育休を取得して子供の育児に関わることで、嫌でも子供と接する時間が大幅に増えます。
そして朗報です。
子供とパパが接する時間が多いと、子供の成長に良い影響があることが分かっています。
お父さん効果で子供の発達にメリット多数
海外の調査や研究で、父親が育児に関わることで期待できる効果があると発表されています。
お父さん効果と言われるそうですが、次のような内容が書かれています。
「幼児期に父親から多く遊んでもらった子供は、自尊心が高まり、自らへの愛情や自信に満ち溢れ、少々のトラブルにもへこたれない強い精神力を持つようになる」とまとめられています。
また、そこにはもう少し具体的な内容も書かれています。
・おもちゃを持って癇癪をおこしたりしない
・「⚪︎⚪︎を持ってきて」という頼み事をすんなりきいてくれる
・初対面の人とでも、躊躇せず会話ができる
・他の子供たちと簡単に打ち解けることができる
・よく笑う
・我慢強い
・会話に対する反応が速い
・新しい遊びへの挑戦を楽しむ
・父親との関係が良好
・父親だけでなく、母親との関係も良好
別の調査で書かれている効果としては、「父親と多くの時間を過ごした子どもは、IQが高い」、「父親と多く会話するほど、言語能力が発達する」、「父親が育児するほど、子どもの社会性が向上する」など、様々なものがありあます。
自尊心が高い子供に育って欲しいと願う親は多いと思います。
父親が育児にたくさん関わることで子供にも良い影響があるのであれば、育休を取得して関わってあげたいと思いませんか?
思い出だけでなく内面の成長も期待できるなら、これほど嬉しいことはないですね!
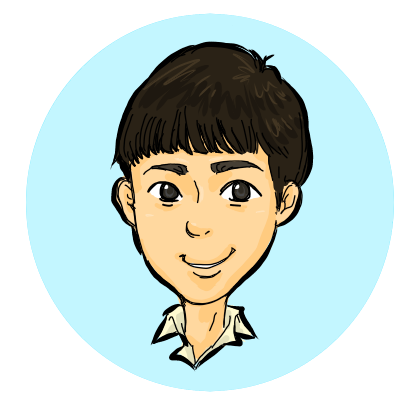
上で紹介した調査や、お父さん効果が書かれているものなどを参考に残しておきます。
気になる方は、下記のものをご参照ください。
「パパがいい!」を増やすことができた
実際に育休を経験してお父さん効果が現れたのか分かりませんが、長男からは「パパとやる!」「パパがいい!」と言ってもらえることが多かった気がします。
ここでひとつエピソードを紹介します。次男の出産のときの話です。
次男の時は前置胎盤になり、妊娠後期に切迫早産で緊急入院となりました。
そうなると家にいるのはパパと長男だけ、そして入院期間は約1ケ月です。
職場には休みをもらって、長男と2人の生活を送ることになりました。
そのときの長男は2歳になったばかり、急に家からママがいなくなりましたが、この1ケ月間はパパといい子に過ごしてくれました。
ごはんも一緒に食べましたし、遊びもお風呂も全部いつもどおりに進めることができました。
この生活ができたのは、普段から育児に関われたからだと思っています。
そして、その前段で育休期間を一緒に過ごしたからこそ、パパでも大丈夫、パパがいいを増やせたと感じています。
とても大変な1ケ月ではありましたが、とても貴重な時間を過ごすことができました。
自分でもよくやったと思っています(笑)
関わったら関わった分だけ、子供は懐いてくれるのかもしれないと思いました。
妻の前置胎盤の経過は別記事にありますので、気になる方はぜひ読んでみてください。
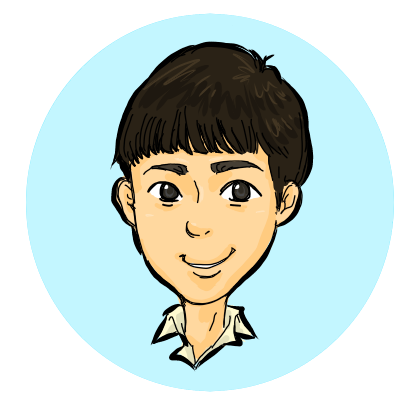
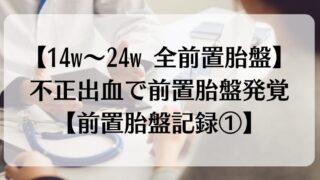
③妻との育児経験値の差を縮めることができる

子供が生まれて抱っこするところから始まり、授乳やオムツ替えなどの育児全てがパパにとって初めてのことになります。
しかし、これはパパだけでなくママも同じで全部初めてのことなので、スタートラインは同じはずです。
子供が生まれて問題がなければ、約1週間くらいで母子共に退院すると思います。
この1週間だけでも、入院中の母親は子供の授乳や沐浴、寝ている子供の表情や息遣いを気にしたりと、多くの経験を積んで成長します。
しかし、父親となると子供に関われるのは面会中の短時間で、そこでできることは限られてしまいます。
これだけでも、退院時点で夫婦の育児経験の差がかなり広がってしまいます。
それに加え、里帰りでもしたら経験の差は数ヶ月単位です。
数ヶ月の期間を毎日育児した母親と、ほぼ未経験の父親が一緒に育児を始めたら、比べものにならない経験値の差ができているのは明らかです。
母親もまだまだ体が本調子にならないのに、一からやり方を教えるところから始め、家事などもやらなければいけないなんて心穏やかに生活できるはずがありません。
育休を取得すれば早い時期から育児に関わることができるので、実践部分での遅れを挽回できると思います。
しかし、母親は出産前から自分で育児について調べたりと知識を蓄えていきます。
父親になるあなたも、ぜひ出産前から育児について考えて調べたりしてみてください。
知識はもちろんですが、父親としての自覚も芽生えてくると思うので、育休中の考え方が大きく変わるはずです。
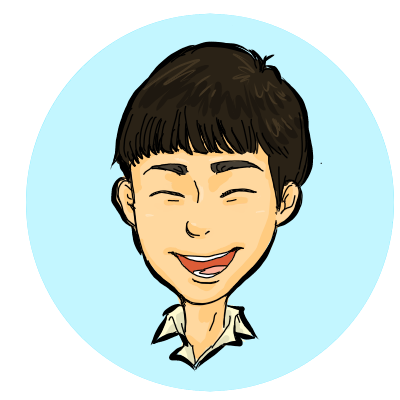
経験値を増やすためにできること
それでは経験値を増やすためにできることは何があるでしょうか?
ひとつの例として、私がやったことを紹介したいと思います。
知識編
ネットで育児について調べるのもいいですが、書籍の方が分かりやすくまとめられているのでオススメです。
我が家は「たまごクラブ」を読んで参考にしていました。
妊娠初期・中期・後期ごとの内容が書かれた3冊に分かれていて、タイミングに合わせた知識を得ることができます。
妊娠の経過や母親の悩みを知ることもできますし、父親に向けた内容の記事も書かれているので参考になる部分もありました。
実技編
実技面では、実際にその時がくるまで経験をするのが難しいことが多いです。
それでも、自治体や企業が主催している「両親学級」に参加することで、沐浴体験を経験できたりするので実践に備えることができます。
そういったイベントなどに参加するのは、モチベーションもあがるので良いと思います。
子供2人目以降の話
第一子で子供が1人だけなら、夫婦2人で子供1人に注力できます。
しかし、2人目以降になると、育児の対象が2以上になるので大変さが増します。
我が家は2歳差の兄弟ですが、2歳0歳の育児が想像以上に大変で疲弊しています。
育休を取得して2人で子育てをしても大変さを痛感しているので、ワンオペだったりの1人での育児が想像できません。
年が近い子供さんの場合なら育休を最大限に活かしたり、育休で手に入れた育児スキルを惜しみなく発揮する場面だと実感しました。
④夫婦の絆が深まる

子育ては嬉しいと感じることがたくさんあると思いますが、逆につらい悲しいと思うこともたくさんあると思います。
母親は出産によって体がいつもと違う状態になり、今までできたことができなくなるので、ストレスに感じる場面は必然的に多くなります。
そんな時期を夫婦2人で乗り切ることができれば、夫婦の絆はより固くなっていくと思います。
気持ちを共有できることの大切さ
ストレスを発散するひとつの手段として、「自分の気持ちを話す」というのがあります。
相手の気持ちを聞いてあげるだけでも良いことだと思いますが、同じように育児を取り組むことで気持ちの共有具合が大幅に変化します。
悩みの原因に対して、育児をしているからこその打開策を提示することもできるはずです。
基本的には育児で休む暇がないことがメンタルへ悪影響を与えていることが多いと思うので、少しでも1人時間を作ってあげるようなサポートができると良いと思います。
夫だからできる産後うつのサポート
こんなニュースを知っていますか?
YAHOO!ニュース
生後4カ月の男児死亡…「妻と息子が出ていった」と夫が通報、駅にいた妻を発見 抱える男児、すでにどこかで溺れさせたか 「産後うつがつらい」と語る38歳、鑑定留置へ…水没させる前、出勤する夫を引き留めていた
ニュースに書かれた情報しかないため、この家庭の背景などは詳しく分かりません。
様々な意見があると思いますが、私はこのニュースを見て感じたことがあります。
産後うつがつらいと感じていた奥さん、「夫が出勤する際、女が夫を引き留めるなど様子がおかしかった」と書かれているように、仕事に行ってほしくないとSOSを出したにも関わらず旦那さんは仕事に行ってしまいました。
急に仕事を休めない気持ちは分かります。
でもSOSをちゃんとキャッチしてあげて、せめて何かしらの安心できる案を提示してあげれなかったのかなと感じました。
さらに言えば、普段からの気持ちの共有や奥さんへのサポートなどができていたのかな?とも思いました。
私の妻も産後うつを経験しましたが、産後うつに限らず体調が悪いときや気持ちが落ちているときには、私が可能な範囲で休みを取って育児を替わるようにしていました。
産後うつの期間はそれぞれだと思いますが、意外と長期化するんだと感じています。
妻も産後1年を経過したあたりから軽快はしてきましたが、それでも完治まではいきませんでした。
もし長期の育休を取得していれば、そういった場合のサポートにも徹することができると実感しました。
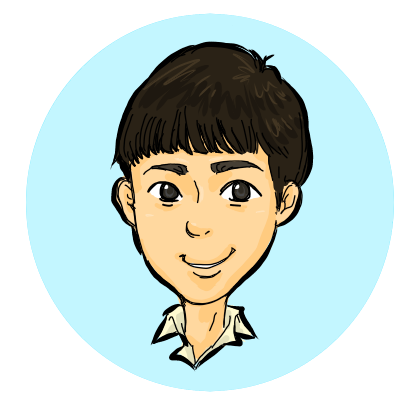
⑤「急」な何かに対応しやすくなる

出産後、入院期間が終わってやっと家に帰ってきたのも束の間、急遽外出しなければならいことが意外とありました。
病院受診や育児用品の買い物などです。
子供が新生児期を終えて、1ケ月検診で問題がなければ外出もすこしずつできるようになるので、それまでは外出にも気を使います。
我が家の様子も少し紹介します。
意外と病院に行くことが多い?
2週間検診、1ケ月検診で出産した病院に行きましたが、それ以外のことで急遽病院受診することがありました。
長男のときは退院後に黄疸が出てきたので、検診以外のタイミングで受診しました。
次男のときは早産だったので、呼吸が安定するまで子供が約1ケ月間の入院でした。
入院中は授乳や沐浴をしてあげるために、家から病院まで通いました。
特に問題がでなければ行くことも少ないかもしれませんが、子供のことなので色々心配になって受診することも多いと思います。
産後の奥さんは運転などもつらい状況なので、運転や待っている間の抱っこなど、旦那さんがやってあげるべきです。
しかし、仕事をしていると急な休みも取りづらいと思うので、育休を取得していつでも対応できるようになっているのが理想だと思います。
育児用品の消耗は激しい!
粉ミルク、オムツにおしり拭きなど、ストックして買っておいたつもりがすぐに消費されていきます。
オムツなんかは、店舗で購入すると物が意外と大きいので、大量に買うのも一苦労です。
我が家はオムツのような大きい物は、通販を利用して購入しています。
それ以外にも、コープデリのような宅配サービスも自宅に商品を届けてくれるのでオススメです。
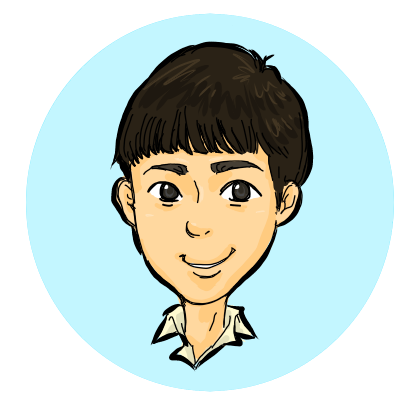
日用品以外にも、普段食べる食事の材料なども買ってこないとなので、少なくとも週に数回は買い物に行きたいところです。
新生児で一緒に連れて行けない時期であれば、旦那さんの力が必要になるのは間違いないでしょう。
まとめ
今回は育休のメリットを5つ紹介しました。
振り返ってみると、育休を取得することで子供にメリットがあるのは当然ですが、奥さんや自分に対しても大きなメリットがあると分かってもらえたのではないでしょうか?
育休取得を悩んでいる方は、こんなメリットもあるんだと参考にしていただき、悔いのない育児期間にしてもらえればと思います。
現在進行形で育休中になりますが、家族みんなで過ごす時間がたくさん取れているので幸せです。
ぜひ皆さんにも、育休生活を楽しんで欲しいなと思います!