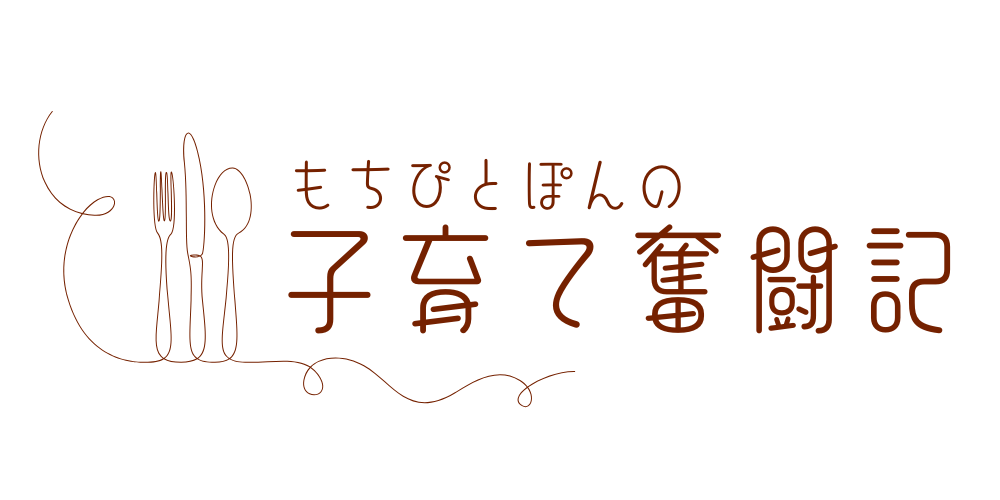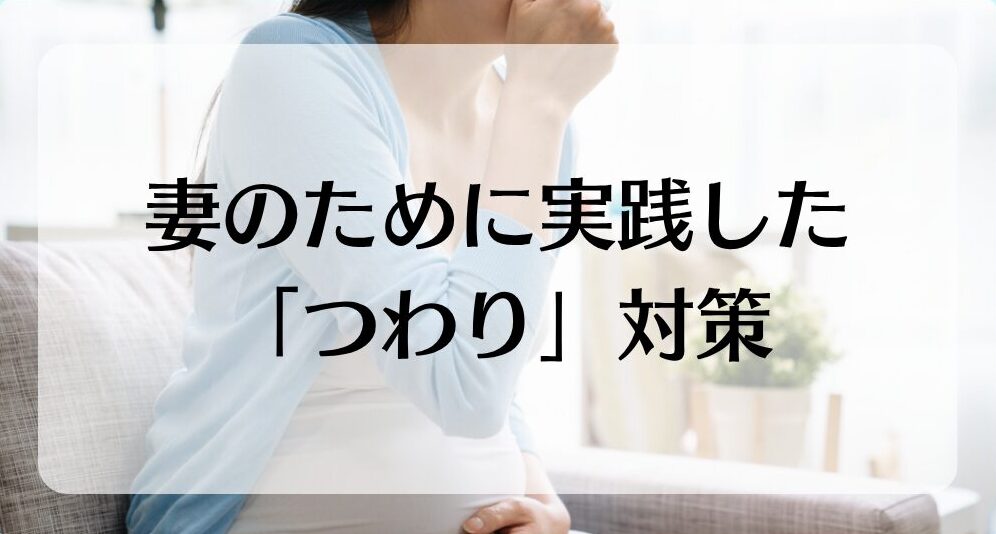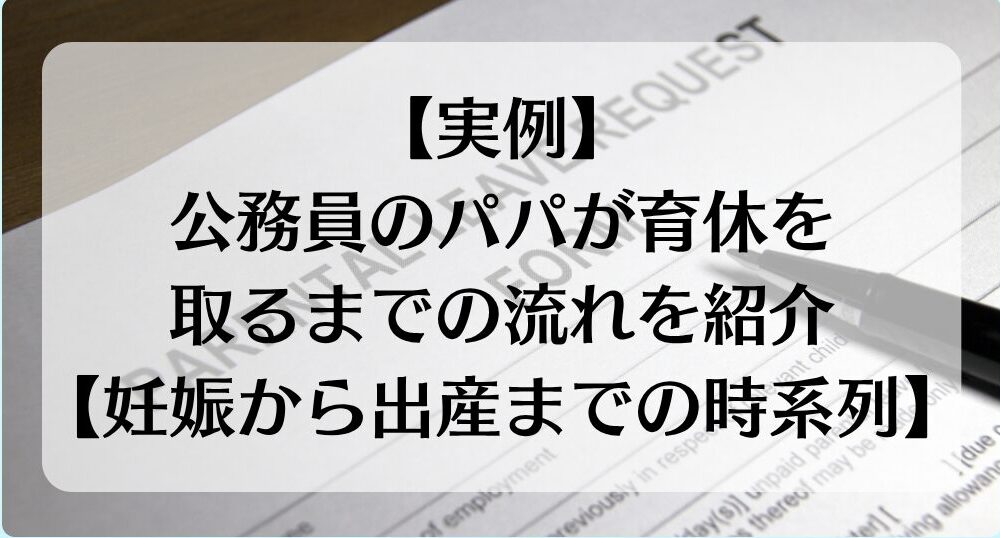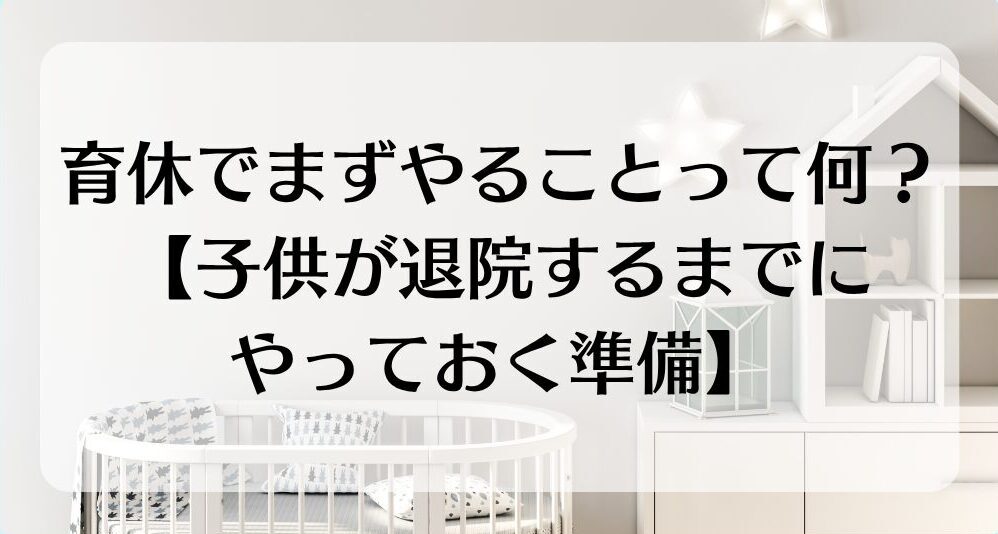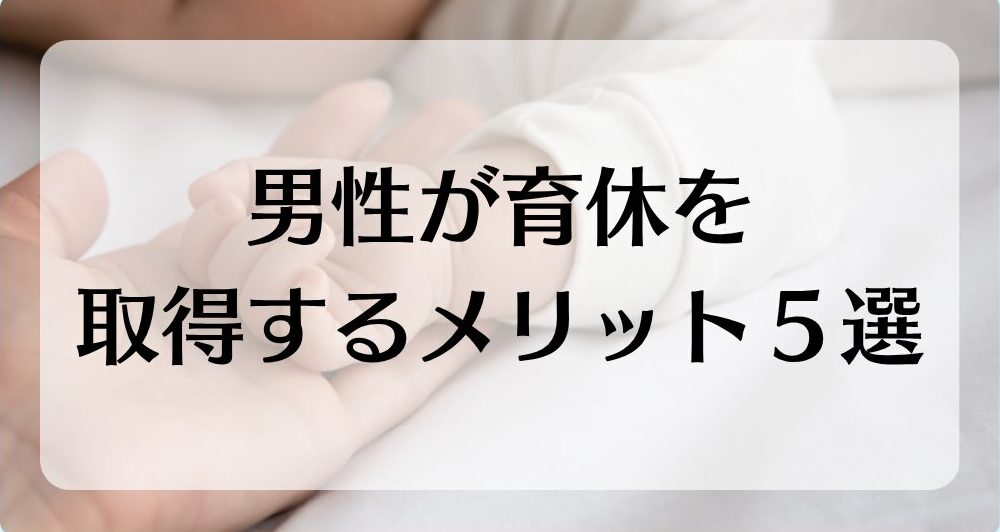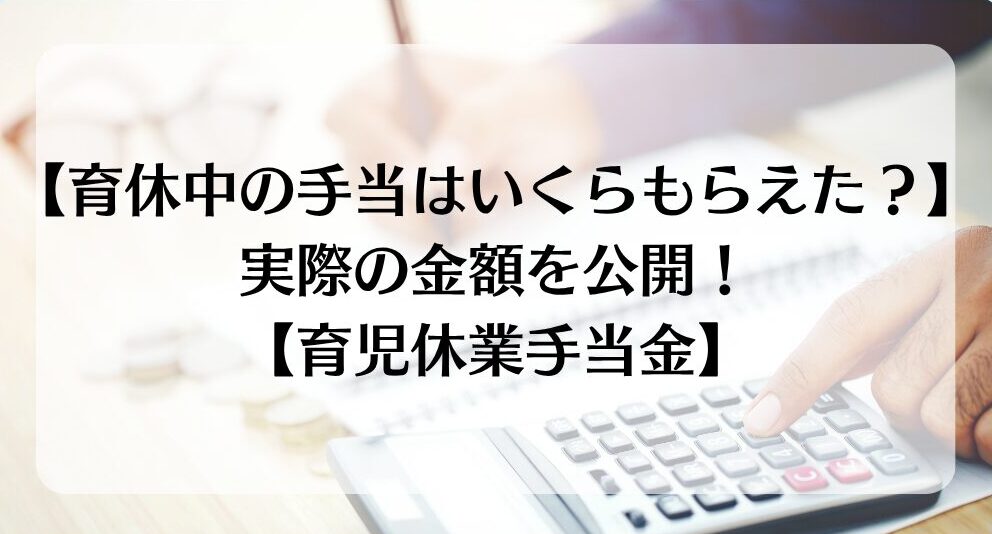【取るだけ育休にしない!】育休前に習得するべきスキルと心得

こんにちは、ぽんです。
この記事では、育休に入る前にできるようにしておくべきスキルと心得についてまとめました。
いざ育休に入っても「こんなはずじゃなかった…」と思わないために、ある程度のスキルや心構えが必要だと思っています。
スキルと心得に分けて3項目ずつあげているので、育休中の生活をイメージしながら読んでもらえると嬉しいです。
育休前になぜ習得が必要なのか
育休前から習得が必要な理由、それはできないことを育休が始まってから覚えても遅いからです。
例えば、このあとに紹介するスキルに『料理』があります。
普段から料理をしない人であれば、作り方が分からないから始まり、自宅の調理道具がどこにあるのかも分からないって人もいるのではないでしょうか?
育休が始まってしまうと奥さんは産後で思うように動けず、分からないことを聞かれるだけでも負担になってしまいます。
育休の大きな目的のひとつは、妻の家事負担を軽減することだと思っています。
産後は負担とストレスをなるべく軽減できるように、サポートができると理想ですよね。
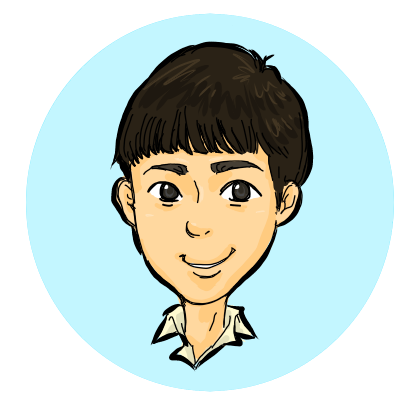
育休が始まったらサポート体制にすぐ入れるように、奥さんの妊娠期間中からスキル習得に励みましょう。
そうすることで、育休中の夫の行動や家事レベルなどを奥さんも前もって知れるので、育休が始まってからの意見の食い違いも軽減できると思います。
習得するべき3つのスキル

それでは、私が考える習得するべきスキルを3つ紹介します。
3つの内容を詳しく説明します。
①料理スキル
料理については説明する必要もないと思いますが、日々の朝食・昼食・夕食を作ることです。
なぜ夫が妻に替わって料理をした方が良いかというと、いくつか理由があります。
料理は万全の体調でないとつらい
まず1つ目に、料理は立ち仕事で体への負担が大きいからです。
産後は思うように体も動かせない状態ですが、その状態で料理を作ることは体を休めるどころの話ではありません。
私の妻は帝王切開でしたが、傷が癒えるのに1年くらいかかりました。
安静を心がけてもそれくらいかかる場合もあるので、少しでも負担を軽減するためにも料理担当は夫が担いましょう。
夫がいると料理を作るハードルが上がる
2つ目に、パートナーが居ると料理の手抜きができなくなってしまうからです。
出産後の経過で段々と動けるようにはなってくると思いますが、そのタイミングで妻が料理担当になったとします。
育休を取得して家にいるのが夫婦2人と子供の場合、作る料理は2人前です。
私1人なら冷蔵庫にあるものを食べていればいいけど……
夫がいるなら足りないし、それなりの物を作らないと……
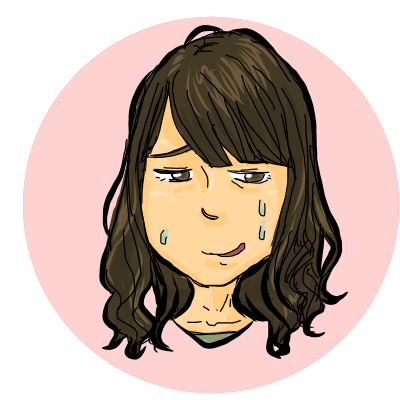
料理は作るのも大変、それにメニュー決めも必要なので負担はさらに増します。
このパターンになってしまうと、妻の本音は……
夫が仕事をしていてくれた方が、毎日の食事の心配が減って絶対に楽だ!
これなら育休を取ってくれなくていいな……

料理は思っている以上に大変なんです。
こうならないためにも、育休を取るのであれば料理は夫が担当すると覚えておきましょう。
料理を作るうえでもまだまだポイントがあります。
単純に作れば良い訳ではありません。
片付けまでしっかりやる
これは誰でも分かりますね。
食べ終わった食器の洗い物はもちろん、コンロ周辺に飛んだ油などもキレイにします。
買った食材の管理も忘れないようにして、冷蔵庫の中で腐った物を放置したりしないようにしましょう。
調理時間は短時間にする
これは意外と重要なことだと思いますが、調理時間が長くなると奥さんの育児負担が増えます。
調理中は子供の面倒を見れないからです。(だからと言って、抱っこしながらの調理は危険ですよ!)
美味しいものを作って喜んでもらいたい気持ちは分かります。
しかし、奥さんが求めているのは「手早く作って育児を替わって休ませて欲しい」だと思います。
料理スキルを補う解決策
調理スキルが足りない夫の場合、1番楽なのは外食のテイクアウトだったり、お弁当や惣菜などになるかと思います。
ただ、毎食そのようなメニューだと金額的にも高くなりますし、食べる側としても飽きてしまいます。
栄養面でも少し心配です。
そこで私が活用していたのは、コープデリのミールキットです。
ミールキットは種類が豊富で、色々なメニューを食べることができます。
材料もカットされていたり、調味料もほとんど一緒に付いてくるので、誰でも簡単に作れるようになっています。
調理時間は15分〜20分くらいで作れるものも多いので、時短にもなります。
栄養士が監修したミールキットなどもあるので、栄養面での心配も解決できますね!
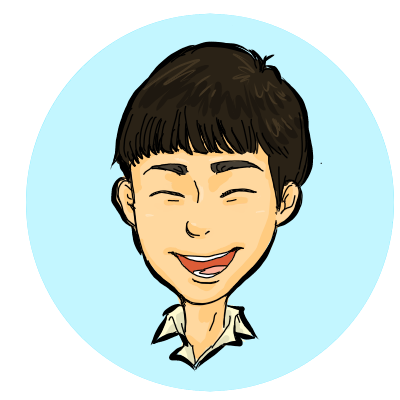
②育児スキル
これも育休ならば絶対にやることになる必須スキルです。
生まれた直後からやらなければならない「授乳」「オムツ替え」「沐浴」が待ち構えています。
授乳
母親の母乳のみで育てる「完全母乳」の場合は、父親が授乳に関われることが少なくなると思いますが、それ以外の「混合」や「完全ミルク」であれば父親も授乳に関わることができます。
我が家は「完全ミルク」だったので、多くの場面でパパが授乳に関われました。
その甲斐もあって、妻には産後の回復に専念してもらうことができたと思います。
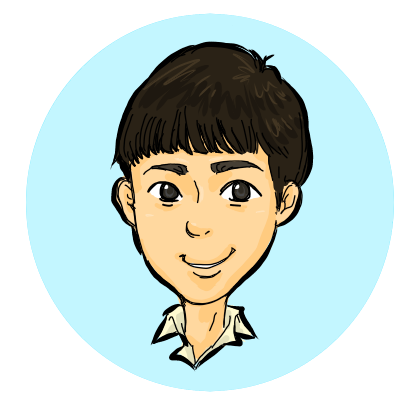
オムツ替え
新生児期(生まれてから27日までの期間)はオシッコやウンチの回数が多いので、オムツ替えは頻回にやってきます。
こまめに替えなければ肌トラブルの原因にもなりますし、そもそも赤ちゃんの機嫌が悪くなったりもするので、泣き止まなくなったりします。
はじめは慣れないので戸惑う部分もあると思いますが、慣れれば簡単に替えることができると思います。
月齢によってウンチも臭くなるので頑張りましょう(笑)
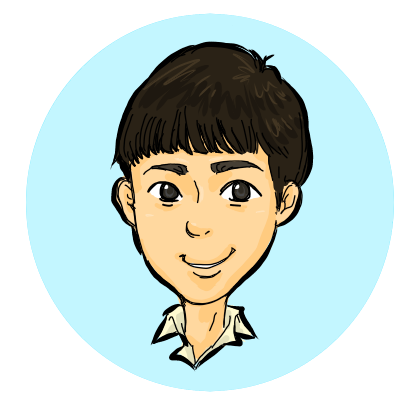
沐浴
沐浴も慣れないうちは、落とさないかと怯えながらやっていました。
それでも毎日やっているうちに慣れてくると思います。
気持ちよさそうに沐浴してくれる我が子を見ていると癒されますよ!
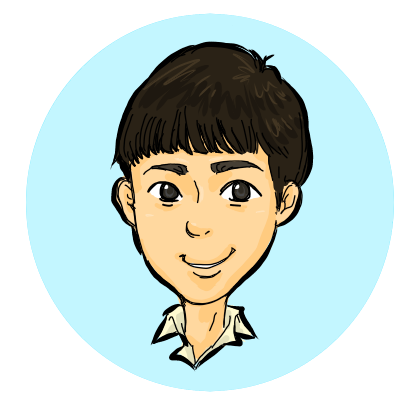
沐浴は自治体で開催しているプレパパの会や両親学級といった集まりの中で、人形を使って体験することができると思います。
参加しておくと手順も学べますし、自宅での沐浴のイメージがより具体的になります。
③名もなき家事を見つけるスキル
名もなき家事という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
料理や洗濯といった家事ではなく、料理関係で言えば少なくなった醤油差しの醤油を補充するなど、細かい部分の家事のことです。
日常にある名もなき家事をあげてみます。
・掃除機のヘッドに絡まったゴミを綺麗にする。
・少なくなった洗剤を補充する。
・シンクの排水溝のぬめり汚れを綺麗にする。
・洗濯機の糸屑フィルターを掃除する。
・冷蔵庫の製氷器の水を補充する。
・無くなったティッシュペーパーを新しいものに替える。
・入りきらなくなったゴミ箱のゴミを片付ける。
・水切りカゴが汚れていたら綺麗にする。
・空気清浄機のフィルターが汚れていたら綺麗にする。
・飲み終わったペットボトルのラベルを剥がす。
まだまだたくさんあると思いますが、これらの名もなき家事を普段やっているでしょうか?
1分もかからない名もなき家事もたくさんありますが、項目が多いだけに意外と大変な家事だと思います。
家族のQOLを上げるためにも、普段から率先して名もなき家事ができるようにしておくと良いと思います。
子供が生まれると、子供関係の名もなき家事が出てくるのも忘れてはなりません。
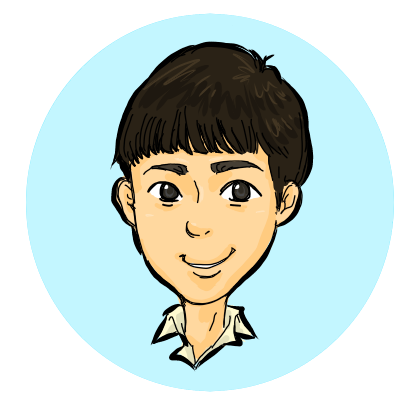
育休前に把握しておく3つの心得

次はスキルではなく、心構えについて書きます。
これも奥さんからしたら分かっていて欲しい部分だと思うので、子供が生まれるまでに自分の気持ちや考えを整理しておくと良いと思います。
心得に関しては、次の3つを説明します。
①パパである自覚を持つ
女性は妊娠すると、日々成長していくお腹の変化を身をもって実感します。
出産を迎えるとお腹の中にいた赤ちゃんが目の前に現れ、体の変化や環境の変化も目まぐるしく変わります。
しかし、男性は自分の体に変化が起きないので、いざ子供が目の前に現れても実感が湧きづらいと思います。
自分が父親になった実感が湧かないと、いざ育休に入っても気持ちの切り替えが難しいと思います。
例えば奥さんの妊娠期間中からサポートを積極的にしてあげて、自分の生活の変化を感じれば、少しは実感も湧いてくるのではないでしょうか?
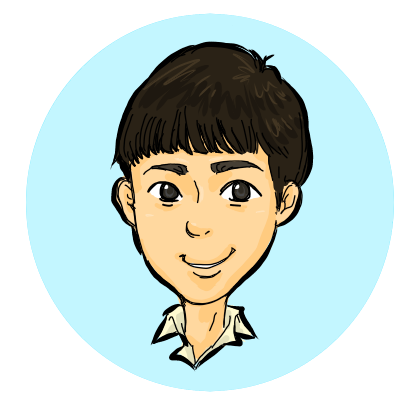
②仕事より育児は大変
育児は家のことなのでノルマや期限がある訳でもなく、少なくとも仕事よりは楽だと思う人もいるかもしれません。
しかし実際に経験してみると、育児は仕事の比ではありませんでした。
生活リズムが子供中心になる
生まれた直後の赤ちゃんは、3時間くらいの間隔でミルクをあげなければなりません。
お腹の空き具合で前後したりもします。
基本は自分たちが決めた時間帯でミルクをあげつつ、間の時間でそれ以外のことをする感じになると思います。
どこかに出かけるにしても、ミルクの時間を気にしなければなりません。
ミルクをあげたら出かける感じになりますし、外出時間が長いと次のミルクの心配もしなければなりません。
自分たちの食事もミルクの間の時間なので、本当に子供中心で1日が進んでいきます。
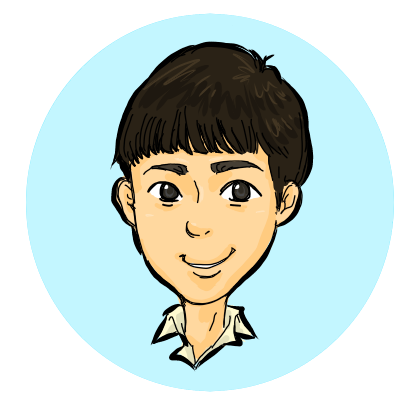
仕事なら自分のタイミングで業務に取りかかることができますが、育児は自分中心でできないので大変です。
そんなところが仕事よりも大変だと思いました。
勤務時間は24時間!?
ミルクの話をしましたが、授乳は夜間も続きます。
授乳だけならまだいいですが、オムツ交換や泣きの対応など、いくつもやることがあります。
育休で2人対応ができれば片方が育児で片方が休憩という作戦も使えるので、ある程度負担を軽減することもできます。
2人で対応できるからといって、夫婦で半々という訳にはいきません。
奥さんは産後の体で負担を減らしてあげるべきなので、パパがしっかりと家事と育児を負担してあげましょう!
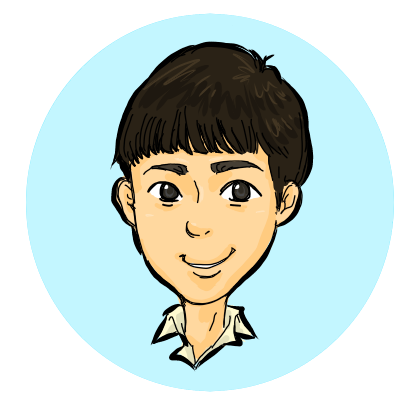
働き詰めでは倒れてしまうので休息の時間もとるべきではありますが、それでも睡眠不足になることは覚悟しておいた方がいいと思います。
育児の方が楽だと感じたら…
育休を実際に経験してみて仕事より楽だったと感じたのであれば、今一度自分のやっていることを見直してみましょう。
家事が全く苦じゃなくて逆に好きだとか、育児が心より楽しいと思っているなら楽と感じることがあると思います。
しかし、多くは慣れないことですし、生活的にも大変なので楽だと思える要素はないはずです。
もしくは、色々な負担が奥さん側に行っている可能性も考えられます。
奥さんよりも自分がしっかり行動できているかを確認しましょう。
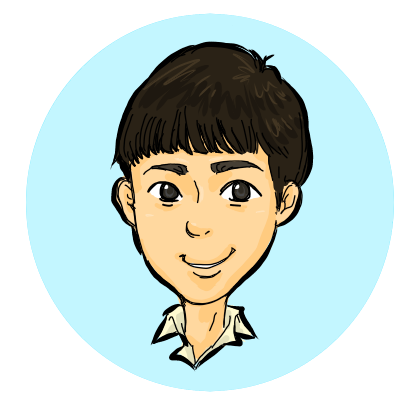
③産後うつは誰しも起こりうる
最後は産後うつの話です。
ここまでの話でも、育児はとても大変だというのが分かってもらえたかと思います。
育児は楽しいや幸せだと感じることもたくさんありますが、反対にストレスと感じる場面もたくさんあるということです。
これに加えて子供の成長で悩んだりと、他にもストレスの原因となる要素がいくつも潜んでいます。
男性の育休が普及する前は、産後うつと言えば母親が注意すべきこととして取り上げられていました。
しかし、男性の育休が普及し始めてからは、男性の産後うつも問題になってきたそうです。
実際に自治体の乳児検診でも、母親の産後うつについてはフォローされていましたが、同席する父親についてはノータッチでした。
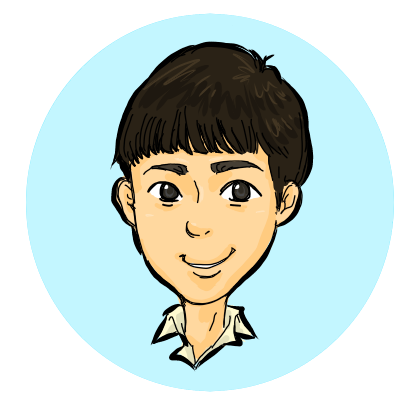
夫婦2人で育児に深く関わるようになってきたため、母親はもちろん父親も気をつけなければなりません。
うつは誰しもなり得ることを頭に入れて、育休期間中は頑張りつつも息抜きなどの休息も忘れないように過ごすべきだと思います。
まとめ
今回は育休前にできるようにしておくスキルと心得についてまとめました。
紹介したスキルは育休後の生活でも重宝すると思うので、積極的に取り組むことをおすすめします。
ぜひ自分のスキルを磨いてみてください!